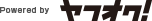■ナビゲーション

2012年08月10日
知ってますか?ハロゲン球と白熱電球の違い!


白熱電球の発明者は、エジソンであるという説やジョセフ・スワンであるという説などもありますが、いずれにしても近代社会に大きく貢献してきたことは確かです。
白熱電球が点灯する仕組みは、中心部のフィラメント(タングステン)に電気が流れることで光ります。
具体的には、フィラメントの電気的抵抗によって2200度~2700度にまで熱せられることによって光りを放つことになります。
白熱電球の特徴としては、電球内から酸素を抜いてアルゴンなどを入れていることで、内部の気圧はとても低く保たれています。
その内部の気圧の低さから、割れたときに破片が飛び散ったり、電球の形状も強度面の理由で皆さんの知っている形となっています。

では、自動車のランプなどにも使用されているハロゲン電球(ハロゲン球)とどこが違うのか?と気になるところですが、発光の基本的な仕組みは同じものになっています。
白熱電球との違いは、内部に入れられているガスが「ハロゲンガス」が使用されていることになります。
一般的には、白熱電球よりもハロゲン電球の方が「明るく長寿命」と言われていますが、その理由はハロゲンガスにあります。
白熱電球もハロゲン電球もフィラメントに使用されているタングステンが高温で蒸発することで、やがて細くなり切れてしまいます。
しかし、ハロゲンガスが内部にあることで蒸発されたタングステンが「ハロゲン化タングステン」という形で再び元に戻る仕組みになっています。
分かりにくいですが、
タングステンが蒸発(気化)
↓
ハロゲンと化学反応
↓
再びタングステンに戻る
という仕組みのようです。
これが原因となって、白熱電球よりも「長寿命」ということになります。
さらに、ハロゲン電球の内部は白熱電球よりも高温になるように設計(250度以上)されていますので、
白熱電球よりも「明るい」
ということになるようです。
白熱電球もハロゲン電球も切れてしまったときには、黒くなりますが、その黒さはフィラメントに使用されている「タングステン」ということになります。
ここで、裏ワザ(という程のものでもありませんが・・・)ですが、ヘッドライトやブレーキランプが切れてしまったその時は、
フィラメントが非常に高温になっています
ユニットの上からでもトントンと軽く衝撃を与えると
一時的に復活することがあります!
試してみて下さい。
Wikipedia [白熱電球]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E7%86%B1%E9%9B%BB%E7%90%83
Wikipedia [ハロゲンランプ]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97
■ナビゲーション
ブログカテゴリー